《令和6年11月1日施行》
道路交通法の一部改正により
原動機付自転車等運転の定義《ペダル付原動機付自転車は「自転車」でなく「バイク」に分類》
が明確化されました。
|
 |
《令和6年11月1日施行》
道路交通法の一部改正により
自転車の危険な行為である
➀ 酒気帯び運転
➁ 携帯電話使用等
に罰則が新設されました。
|
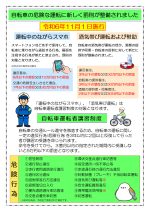
|
《令和5年7月1日施行》
道路交通法の一部改正により
① 電動キックボード等(特定小型原動機付自転車)の交通方法等
② 自動配送ロボット(遠隔操作型小型車)の交通法等
について整備されます。
|
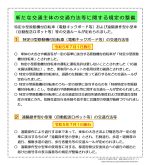
|
《令和5年4月1日施行》
道路交通法の一部改正により
① 運転者がいない状態での自動運転《特定自動運転)に関する
許可制度の創設に関する規定
② 自転車乗車用ヘルメット着用義務化に関する規定
について整備されました。
|
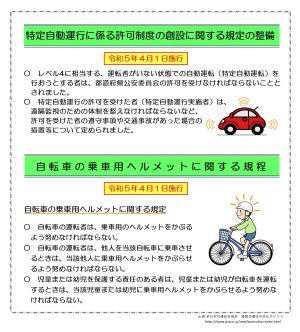
|
《令和4年10月1日施行》
道路交通法の一部改正により
① 安全運転管理者の関する規定
② 停車および駐車禁止場所から除外する対象の拡大に関する規定
について整備されました。
|
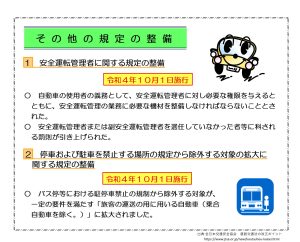
|
《令和4年4月27日公布・・・3年以内に施行予定》
運転免許証と個人番号カード(マイナンバーカード)の一体化に
関する規定が整備されました。
|
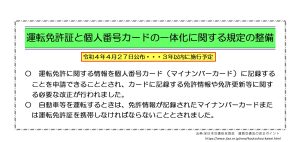
|
《令和4年5月13日施行》
高齢運転者による交通事故情勢等を踏まえて
① 運転技能検査(実車試験)の導入
② 安全運転サポート車限定免許の創設
など高齢運転者対策の充実・強化を図るための規定が整備されました。
|
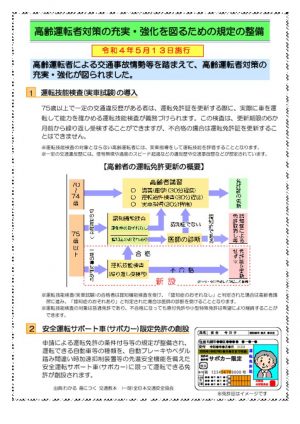
|
《令和4年5月13日施行》
道路交通法の一部改正により、
第二種免許および大型免許、中型免許の受験資格が見直し(緩和)
されました。
|
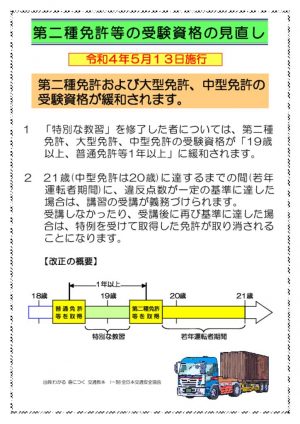
|
《令和2年12月1日施行》
普通自転車の定義に係る規定等が見直し・整備されました。
① 普通自転車の定義に係る規定等の見直し
② 駐車及び停車等に関する規定の整備
③ 初心運転者標識に係り規定等の見直し
|
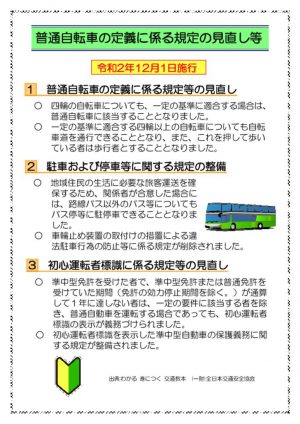
|
《令和2年6月30日施行》
道路交通法の一部改正により
① いわゆる「あおり運転」が妨害目的の運転として道路交通法に
新たに規定されました。
|

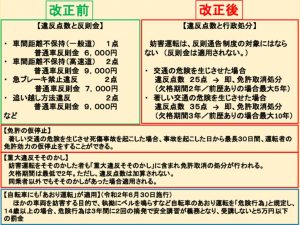
|
|
《令和2年7月2日施行》
いわゆる「あおり運転」が道路交通法に規定されたことに伴い、
「自動車運転死傷行為処罰法」が改正されました。
⑴ 走行中の車の前で止まる等の妨害運転が「危険運転致死傷罪」
に問われることになりました。
|
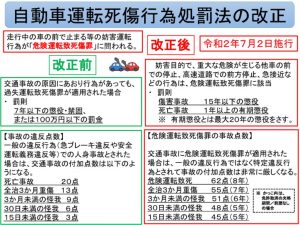
|
《令和2年4月1日施行》
自動車の自動運転技術の実用化に対応するための規定が整備され
ました。
|
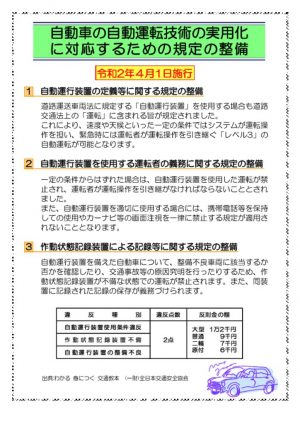
|
《令和元年12月1日施行》
道路交通法の一部改正により
① 携帯電話等による「ながら運転」の厳罰化
② 「運転経歴証明書」取得対象の拡大
③ 「運転免許証再交付」対象の拡大
④ 「電動バイク」の自動車区分の変更
の4点が改正されました。
|
 改正のあらまし |
《平成29年3月12施行》
①準中型自動車と準中型免許が新設されました
車両区分に新たに準中型自動車が設けられ、普通・準中型・中型・大型の4区分となり、準中型自動車の新設に伴い、準中型免許が導入されました。
|
 改正道路交通法のポイント 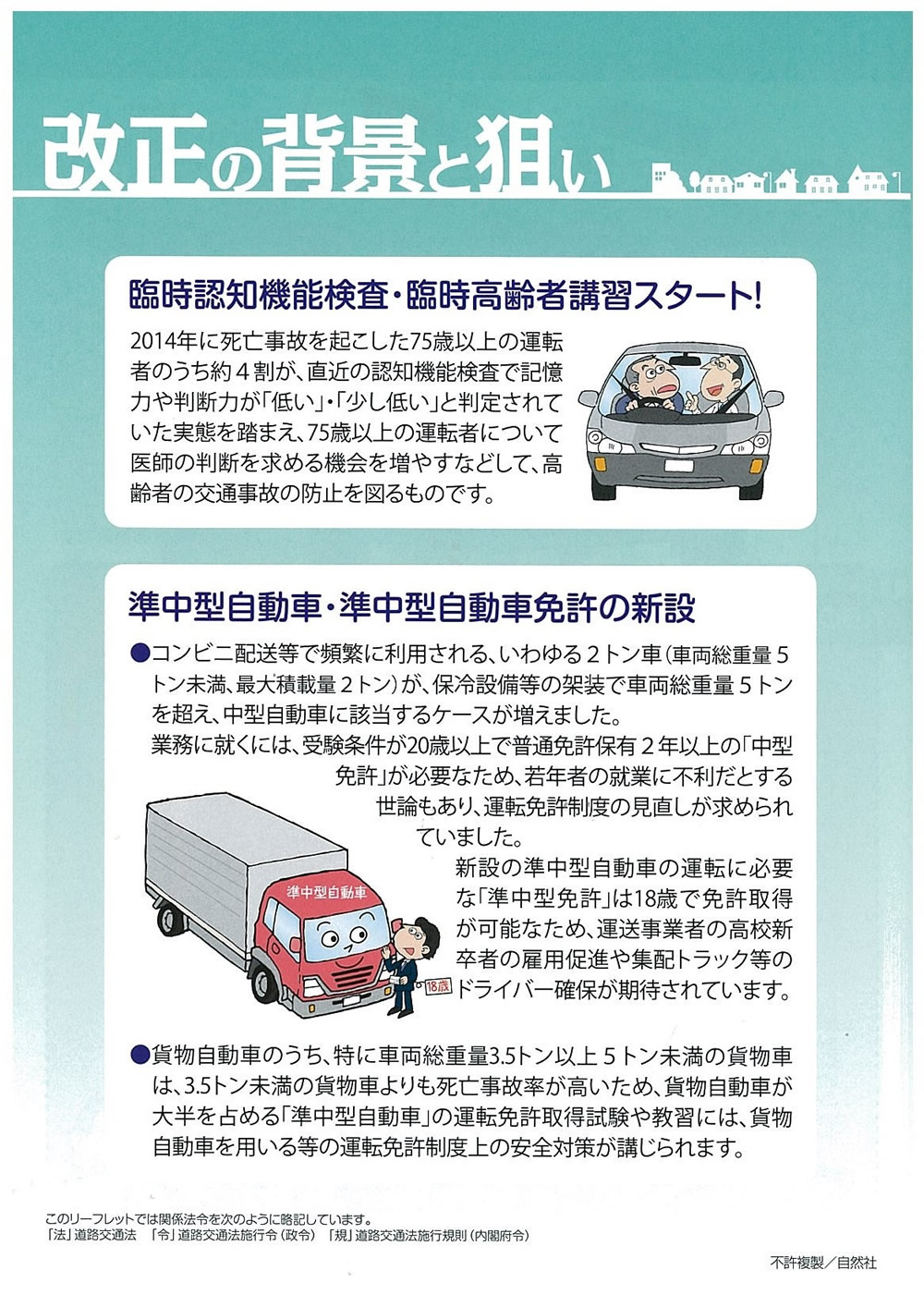
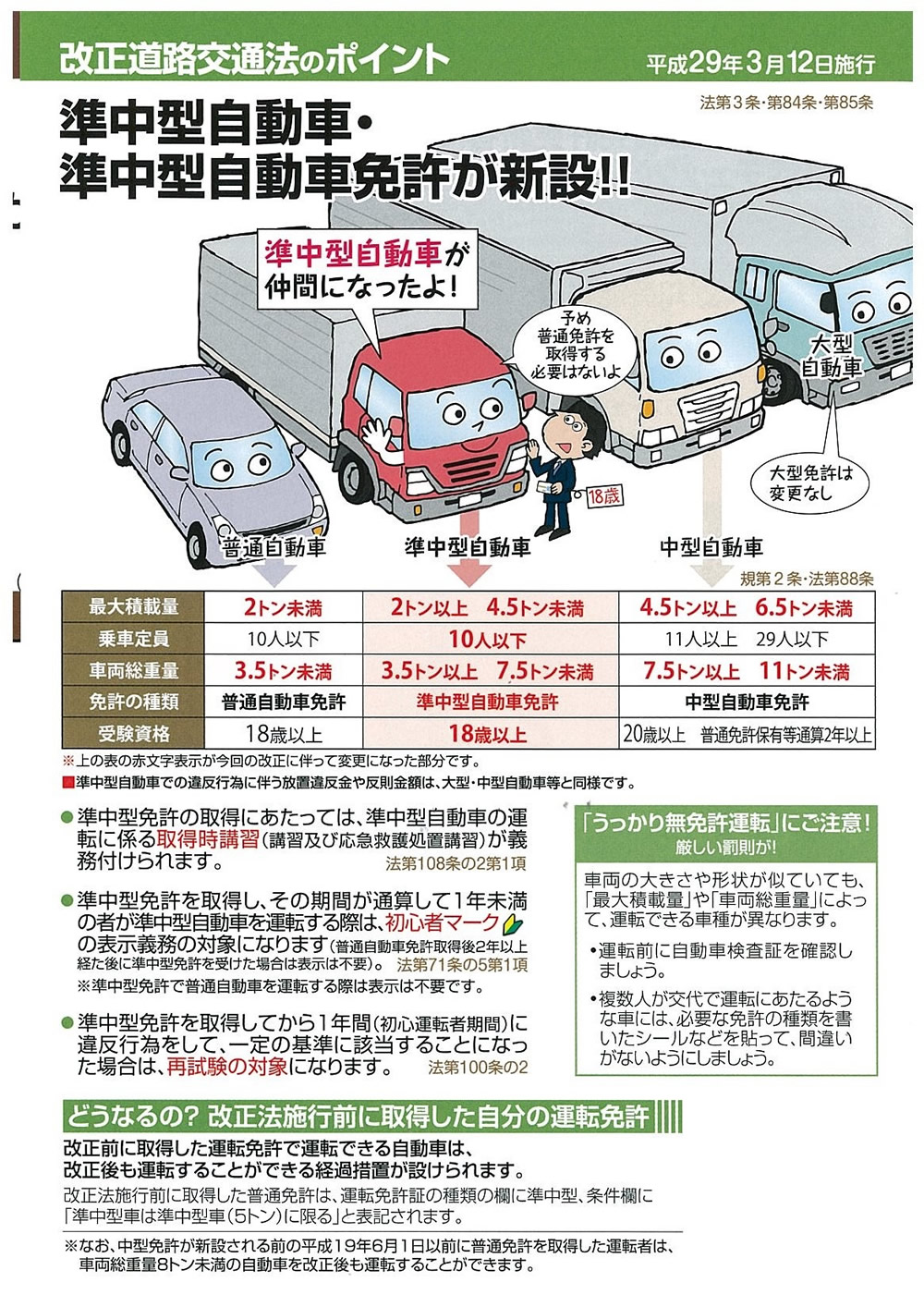
|
②75歳以上の高齢ドライバー対策が強化されました
75歳以上の高齢ドライバーについては、3年に一度の免許更新の際に、記憶力や判断力のレベルを判定する「認知機能検査」の受講が義務付けられていますが、更に、「臨時認知機能検査」 「臨時高齢者講習」等の規定が整備されました。
|
 改正背景と狙い 
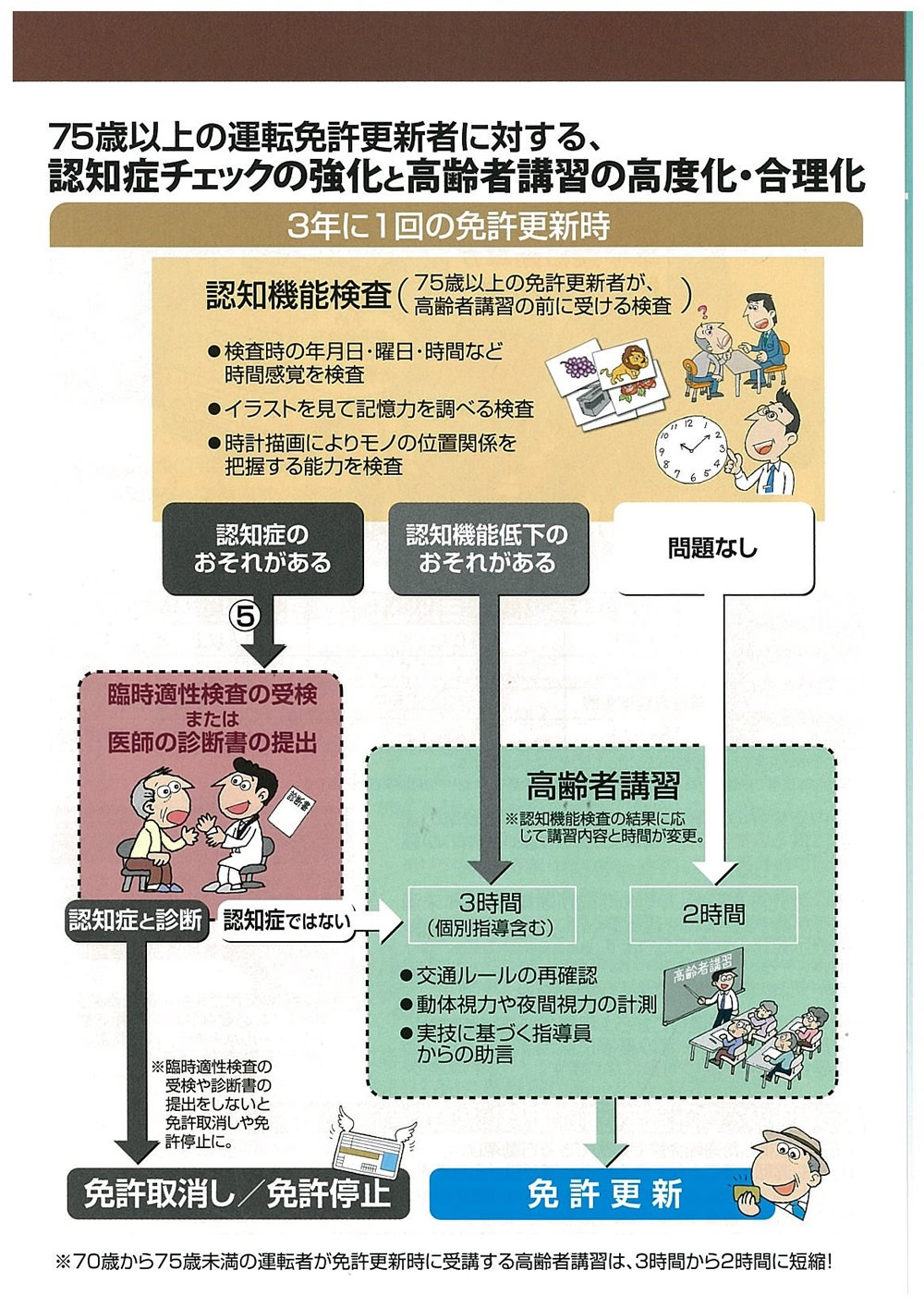
|